プラズマCVD装置の歴史と産業動向
掲載日 2025/10/06
1. プラズマCVDの概況
本稿では、プラズマCVDの装置および産業動向について紹介する。
プラズマCVD(Plasma CVD、PECVDまたはPCVD)は、原料ガスを減圧下で発生させた低温プラズマ(グロー放電)を利用し、そのプラズマ状態で分解や化学反応を促進して成膜を行う手法である。従来のCVDと比較すると、室温から600℃程度までの低温で高品質な膜を形成できる点に特徴がある。
低温成膜が可能であることから、メタル配線プロセスなどのように高温処理が困難な工程に有効である。さらに、RF(無線周波数)出力や周波数などを制御することで、堆積される膜の特性を精密に調整できる点も大きな利点である。
2. プラズマCVDの歴史
プラズマCVDを利用した薄膜形成手法の半導体デバイスへの応用は、すでに1960年代から議論されていた。しかし当時は、プラズマという複雑な現象を適切に制御できる技術や量産装置が未整備であったため、実用化には至らなかった。
その後、1970年代後半から1980年代にかけて、半導体の微細化が進展するなかで配線への熱影響が課題として注目され、プラズマCVD装置の開発が活発化し、急速に実用化が進んだ。1979年にはPlasma-ThermがPE-CVDシステムを開発した[1]。さらにオランダASMの日本法人であるASM Japanがいち早く国産化に取り組み、当時量産されていた横型LPCVD装置にプラズマ機能を組み込んだバッチ式プラズマCVD装置を開発・販売した[2]。これが今日のプラズマCVD装置の基盤となっている。
1987年には米Applied Materialsがウエーハを一枚ずつ処理する枚様式マルチチャンバー型プラズマCVD装置「p-5000」を発表し、米Novellus Systems(現米Lam Research)がセミバッチ型装置を開発するなど、多くの企業が相次いでプラズマCVD装置の開発に参入し、市場シェアは急速に拡大した[8]。
1990年代に入ると高密度プラズマ装置が登場し、その技術をもとに200mmや300mmウエーハに対応する高密度プラズマCVD装置が開発されるなど、さらなる進展を遂げた。現在では、プラズマ技術はプラズマALDとしても活用され、最先端半導体の成膜に不可欠な技術となっている。
続きをご覧いただくにはログインしていただく必要があります。
関連特集
関連カテゴリー
「プラズマCVD装置の歴史と産業動向」に関連するカテゴリーが存在しません。
注目企業



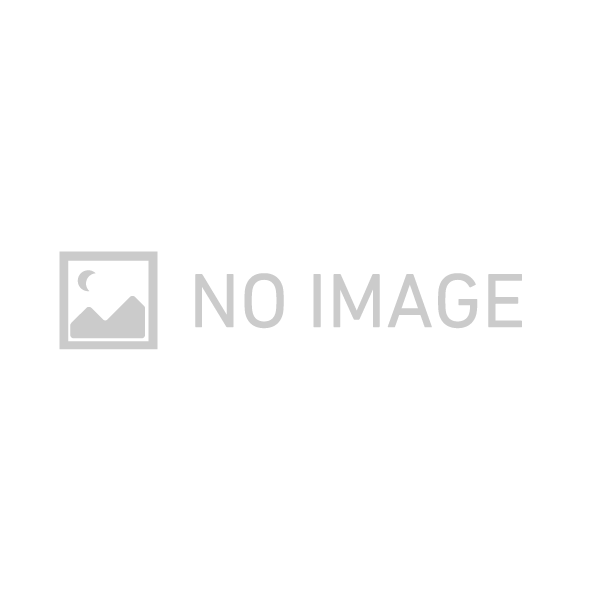 Applied Materials,Inc
Applied Materials,Inc

